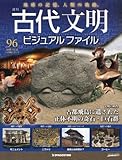地面からにょっきり突き出た奇妙な石。飛鳥奇石群シリーズ、第9弾はマラ石です。ストレートすぎる名称だからか、明日香村観光開発公社の「飛鳥周遊マップ」からも黙殺されています。
目立たないので見逃されがち

マラ石(まらいし)は国営飛鳥歴史公園の祝戸という地域にあります。石舞台古墳の南西です。たいていの観光マップには載っていませんし、観光案内の標識にも小さく書かれているので見逃されがち。でも当ブログの読者の方ならぜひ足を運んでほしいスポットです。

もとは直立していたのか?

マラ石は文字通り、男性性器のような高さ一メートルほどの石です。もともとは垂直に立っていたという説もあり、時の経過とともに徐々に傾いているそうです。なんかリアルですな。でもこの石が傾くと不作になるという言い伝えもあるので、村人が度々起こしていたみたい。
石田茂作氏の命名で広がる

マラ石という直球な名称は、元国立博物館館長であり仏教考古学者の石田茂作(1894〜1977)氏が昭和11年に発表した『飛鳥時代寺院跡の研究』という著書の中で記述したことから広まりました。おんだ祭が行われる飛鳥坐神社の境内をはじめ、明日香村にはこのような陰陽石が点在しています。

五穀豊穣と陰陽信仰の関連

明日香村出身の考古学者・網干善教(あぼしよしのり:1927〜2006)氏は、マラ石と五穀豊穣や陰陽信仰との関連を述べています。もともとこの地方にはそういった信仰が根付いていたのでしょうね。
フグリ山とマラ石で一対か

またマラ石と、近くのフグリ山とで一対になっているという説もあるそうです。マラ石の西側にある山はミハ山というのですが、別名はフグリ山。フグリというのは陰嚢、つまり金玉のことですね。言われてみるとそう見えなくもない……かなあ。
マラ石は立石の一種?

ところでこのマラ石を立石の一つであると考える説もあります。立石はこの地方にたくさんあり、結界を示した石であるとも道標であるとも言われています。
上居(あげい・じょうご)の立石

これは上居(あげい・じょうご)の立石。石舞台古墳から、多武峯方面へ向かう155号線の途中にあります。長方形の岩で、南を向いています。高さ2メートル、幅1.7メートルぐらい。
岡の立石
岡の立石は岡寺にある高さ3メートルの石です。ただこの石は山道を200メートルも登った林の中にあるので、残念ながらお寺の入り口で引き返して見られませんでした。
他にもある飛鳥の立石
立部(たちべ)の立石は定林寺跡に、豊浦の立石は甘樫坐神社の境内に、川原の立石は川原寺の飛鳥川で発見されましたが現在は埋め戻されて見ることはできません。結局のところ、立石であるにせよマラ石であるにせよいつものフレーズ「はっきりとしたことはわかっていない」と言わざるを得ません。(2013年02月03日訪問)【麻理】
参考文献
地図&情報
マラ石(まらいし)
住所 :奈良県高市郡明日香村祝戸
電話 :0744-54-5600(明日香村教育委員会文化財課)
時間 :見学自由
休業日:年中無休
入場料:無料
駐車場:なし